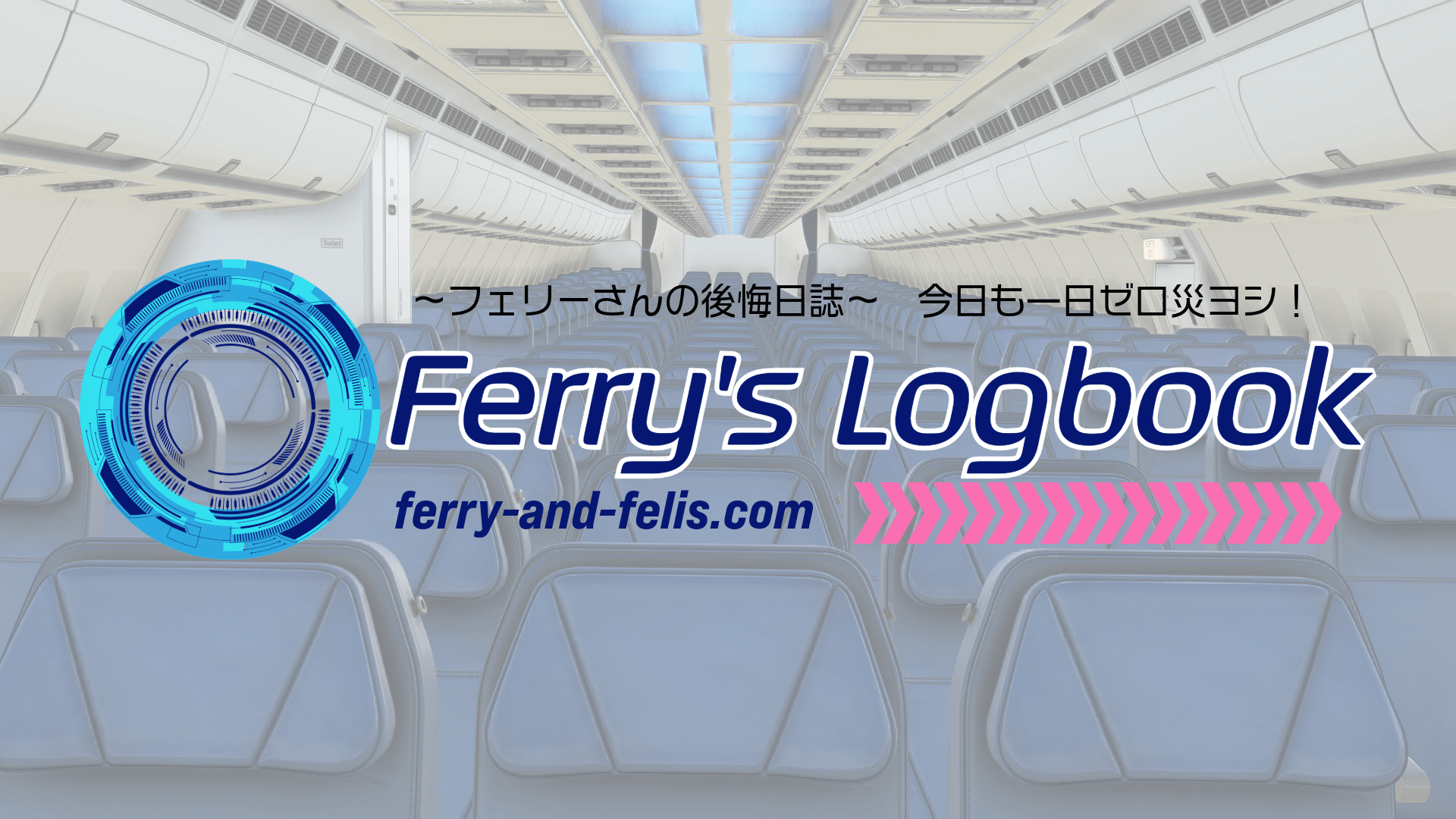職業訓練事業所での体験記:一般的な就労支援との相違点、そして心の内
この度、過去に体験した就労継続支援A型事業所での経験について、その運営方針と利用者への影響を客観的に報告するとともに、その中で私がどのような心境を抱いたのか、その心の軌跡をお伝えしたいと思います。一般的な就労支援事業所とは異なる、独自の価値観に基づいたプログラムは、私の心に深く刻まれるものとなりました。
【おこおわり】
今回の記事はホスティング先の規約を検証し、それに合わせて半分ほど調整を行っています。修正前は障害観や死生観など極めてグロテスクで差別的な内容でした。だいぶソフトに調整を行いましたがそれでもPSTDなどを持っている方にとっては辛いテキストである可能性は否めません。どうかご自身の状態に合わせて読まれるか判断することを強く推奨します。
1. 事業所の概要と方針
私は当時公共職業訓練を経験していますが、就労スキルの確立のため、就労継続支援A型事業所Z社での訓練を利用しました。Z社は令和創業の比較的新しい事業所でしたが、その運営方針は独自の哲学に基づくものであり、一般的な就労支援の潮流とは一線を画していました。
この事業所が目指していたのは、主体性を持たず、与えられた指示に忠実に従う利用者像の育成でした。事業所の利益を最大化するためには、管理コストの削減が不可欠であり、個々の利用者が独自の意見や行動をすることは非効率と見なされたためです。
2. 訓練プログラムの特徴と利用者への影響
Z社での訓練は、以下の項目に集約されるものでした。これらの訓練を通じて、利用者は特定の思考様式を身につけることになりました。
- 個人の問題としての内在化: 事業所内で生じる業務上の問題やトラブルは、組織の不備ではなく、あくまで利用者の個人的な問題として解決するよう指導されました。これは、指導コストを削減するための効率的な手法であり、「自分が悪いのだ」という極端な自責思考を利用者に根付かせる結果となりました。
- 合理的配慮や環境調整の否定: 合理的配慮は「わがまま」と見なされる傾向がありました。事業所は公的給付金への依存度が高く、設備投資や利用者・スタッフへの教育コストを最小限に抑える運営方針でした。そのため、個々の特性に合わせた環境調整の要望は受け入れられず、配慮を求める利用者は協調性を欠く存在として扱われました。
- 特定の障害特性を持つ利用者の評価: 特に知的障害を持つ利用者など、指示に忠実で大人しい特性を持つ利用者は高く評価される傾向にありました。一方で、精神系の障害を持つ利用者は、比較的高い知見や主体性を持ちやすいため、事業所の運営方針と対立することが多く、指導の対象となりがちでした。
- 障害そのものの否定: 事業所は障害者支援施設でありながら、障害を弱みや恥ずべきものと捉え、それを隠すように指導しました。自己分析や自己理解を深めることを推奨せず、他者軸で健常者に同化することを目標とするようなプログラムでした。これにより、利用者は自身の特性を活かすための方法を見失いがちでした。
- 差別やハラスメントへの順応: 訓練を通じて、不条理や差別的な状況に耐え抜くことが美徳とされました。これにより、利用者は問題に直面しても抵抗する力を失い、思考停止の状態に陥ることがありました。
3. 不適切な運営体制とその背景
Z社は、サービス管理責任者の長期不在や、指定取り消しの要件に該当する可能性のある運営を行っていました。業務内容も、コンプライアンス遵守ではなく、一般的な市場の需要とはかけ離れた、社長が所有する特定の企業との取引に依存するスタイルでした。
これは「循環取引」といい、Z社の運営の根幹をなすものでした。具体的には、社長が個人的に所有する別会社から仕事を受注し、事業所が「仕事のようななにか」を納品することで売上を計上するという仕組みです。これにより、外部からの仕事がなくても売上が確保され、公的給付金の申請を正当化することができていました。
この仕組みは、利用者が従事する作業が「公的給付金を引き出すためのアリバイ」として機能することを意味します。市場価値を伴わない仕事でも売上として計上でき、必然的に生産性や品質向上のための改善は行う必要性が出ないため、主観的・感情的な評価が中心となりました。
4. 訓練後のキャリア形成への影響
Z社での訓練を終えた利用者は、特定の思考様式を身につけた状態で社会に戻ることになります。
- 入職先企業の選択における困難: 訓練で身につけた「理不尽に耐えること」は、一見すると忍耐力があるように見えますが、本質的には思考停止と無抵抗を意味します。このため、ハラスメントが常態化しているような不適切な労働環境の企業を、かえって「甘い」と感じて選択してしまう傾向が見られました。
- 自己肯定感の低下と孤立: 組織の問題を個人の責任として捉える癖は、自己肯定感を著しく低下させます。また、問題解決のために外部の支援を求めるという発想が失われるため、孤立しやすくなります。
- 医療・福祉リソースの再利用: 独自の価値観に基づく訓練は、心身に大きな負荷をかけ、結果として新たな精神的・身体的困難を引き起こす可能性があります。これにより、さらなる医療的・福祉的支援を必要とする状況に陥ることも考えられます。
5. 逆境体験が私に与えたもの:心の軌跡
この客観的な事実の羅列は、私の心に深く刻まれた傷跡です。Z社での日々は、単なる就労支援ではなく、私の心を破壊し、価値観を歪ませる、まさに「逆境体験」でした。
そこから私は、自分自身を深く疑うようになりました。何が起きても「自分が悪いのだ」と。それは、世間一般の常識からかけ離れた、非常に歪んだ「自責思考」でした。配慮を求めることは、自分の「わがまま」だと指導され、私はいつしか自分の苦手なことを口にすることさえも躊躇するようになりました。
事業所は、障害を隠すべきもの、恥ずべきものだと教え込まれました。自分の内側にいる「障害」という存在を、私は深く憎むようになりました。自己分析を放棄し、健常者に同化することを目標とするようなプログラムは、私から自己肯定感と、自分の強みを言葉にする力を奪いました。
そして、不当な扱いを感情をなくして受け入れる術を身につけた私は、理不尽に耐えられる人間として社会に戻りました。その結果、離職率の高いブラック企業として知られる家電量販店に転職してしまいました。面接では「どんな苦労にも耐えられます」とアピールしました。それは、真の忍耐力ではなく、ただの思考停止と無抵抗でした。その後心身に支障をきたしたのとそれに関連する交通事故がきっかけで退職をしました。
ある日、認知が深く歪んだ私は、精神科のクリニックで患者さんに対し、平然と「努力が足りないから障害が起こるんだよ」という言葉を口にする自分がいました。その言葉が、障害を持つ私自身から発せられたという事実に、私は言葉を失いました。あの時、私を駆動していたのは、もはや私自身の心ではなく、事業所で植え付けられた異常なマインドセットだったのです。
この経験は、私にとって大きな傷となりました。しかし同時に、自らの心がいかにして歪んでいったのか、そして、そこからどう回復していくべきかを知るきっかけにもなりました。次回は、この絶望的な体験に対する「答え」として、現在受けている、全く異なる方針の就労支援についてお話ししたいと思います。